経営者の仕事とはいったい何で、日々をどのように過ごさねばならないのでしょうか―。 これはなかなかの難問だと思います。 経営者はいうまでもなく、リーダーでなくてはなりません。 会社を代表する存在でなくてはなりませんし、事業戦略の構想者でなくてはなりません。 経営理念の策定者でなくてはならず、また、その伝道者でなくてはならないはずです。 一方で、具体的な仕事に関しては、「担当がないのが経営者」とも言われます… みさきニューズレター9回目となる今回は、戦略論の大家・神戸大学大学院の三品教授に戦略論ではなく、あえて経営者論を語っていただきました。 「創業経営者と専門経営者の競争論」に始まった対談は、論が進むにつれドンドン鋭さを増していきます。 大企業で創業者のような「マンデート(使命感)」をもった経営者を生み出すための手法は何か、「経営者に多くを求めすぎるな」と警鐘を鳴らす三品教授が考える経営者唯一の資質とは何か、そして安易に規模を追うことへの訓戒と、経営者の日々の過ごし方に対する胸を突く言葉。 今回のみさきニューズレターはいつになく辛口で、しかし日々、身を削るように経営している人には強く共感を呼ぶ内容になっていると思います。 「リーダーが持つべき唯一の資質は真摯さである」。ドラッカーの言葉です。 松下幸之助翁も「社長は熱意にかけては最高やないといかん」と書いています。 個人的な体験でいえば、投資先企業の創業社長に初めてお会いした時に「真剣にやっている人は、真剣にやっている人のことがわかるんですよ」と言われた瞬間が思い出される内容になりました。
みさき投資株式会社
代表取締役社長
中神康議
中神:みさき投資では三品先生の戦略理論をチーム全員で共有し、投資でも活用しています。一方で先生は「戦略は人に宿る」ともおっしゃっています。実際、先生の本を読むと独自の経営者論や経営者観が端々に現れています。 このニューズレターのテーマは「みさきで良い経営を考える」なのですが、良い経営を生むのは他でもない、経営者自身です。そこで今日は戦略論の大家・三品先生にあえて経営者論を語っていただきたいと思います。 先生の経営者論の中で私が特に印象に残っているのは、『戦略不全の因果』に登場する経営者競争の段階論です。 戦後日本企業は目覚ましい飛躍を遂げたわけですが、その時代の名経営者とされる松下幸之助や本田宗一郎は何といっても創業経営者。だから彼らがビジネススクールで教育を受けた程度の欧米の専門経営者に勝てたのは、いわば当たり前だった。 でも創業世代が引退し、専門経営者同士の競争になってからは日本は負け続けている。それは経営者としての専門性を磨き切っていなかったからだと。 やがて米国ではベンチャー企業を率いる創業経営者が次々と現れたので当然負ける。韓国や台湾・中国にも創業経営者の時代が到来した。こうなると元々専門性が低かった日本の経営者は全く歯が立たないという話です。 三品:創業経営者と専門経営者の最大の違いは、創業経営者は自動的にすべてにおいて第一人者だということです。 あの倉庫はなぜここにあるのか、なぜ入口は東側にあるのかなど、会社の中で知らないことはない。単に知っているというのではなく、事業への思い入れや愛着、そしてこれまで支えてくれた人への感謝の念も圧倒的に強い。これは既に会社が出来上がってから入社した専門経営者とは大きな違いです。 では自分自身で創業しないと全くダメなのかといえば、それもちょっと違う。その好例は本田技研の河島喜好です。ホンダの飛躍を生み出したのは実は本田宗一郎ではなく、河島喜好です。彼が米国に現地生産工場を作る決断をし、それを実行したのです。創業家でも出資者でもないのにそんなに強力な経営判断ができたのは、彼がホンダが立ち上がるときから会社にいて、会社の成り立ちを本田宗一郎と同じくらい知っていたからです。 だから大事なことは血筋でも資本でもありません。自分で一からやることが創業経営者を創るのです。 中神:先生は創業経営者には「マンデート」、すなわち使命感が備わるともおっしゃっていますが、そのマンデートもここから生まれるのでしょうか。 三品:創業期を知っている経営者には、自分たちが厳しい競争環境を生き残ることができたのは、社会からの応援があったからだという理解があります。その「有り難い」という気持ちから、なんとか社会に報いなくてはというマンデートが生まれてくるのです。 中神:まさに報恩感謝の気持ちということですね。 日本にはこれまで何度か、新しい会社が次々と興される時期がありました。例えば朝鮮戦争の頃や、高度成長前夜の時代。その頃に入社した人は創業者でなくても会社を隅々まで知り、マンデートが培われたはずです。でも、現在多くの日本企業はそうした創業の時代からは遠い成熟期を迎えています。 果たして日本はこれからもう一度起業を促し創業経営者を創ってゆくべきなのでしょうか。それとも専門経営者を育成してゆくべきなのでしょうか。 三品:それは両方です。 焼き畑をしないと土地が荒廃するように、企業活動の主体も本当はある程度リニューアルした方が良いのです。 畑が焼けている瞬間は悲劇に見えますが、実はそこからすくすくと新芽が育ってくる。だから火だるまになっている会社があっても、本当は放っておけばいい。社会としては瀕死に陥った会社を税金で救うのではなく、新芽を大切にするべきなのです。 反対にそうは言っても既にある事業体を継続した方が合理的な場合もあります。そういうときには専門経営者の育て方を考え直した方が良いでしょう。 それは創業経営者ではない中で、いい仕事をした人たちを見つめるとよく分かってきます。私の中でのNo.1は、信越化学工業の金川千尋さんです。
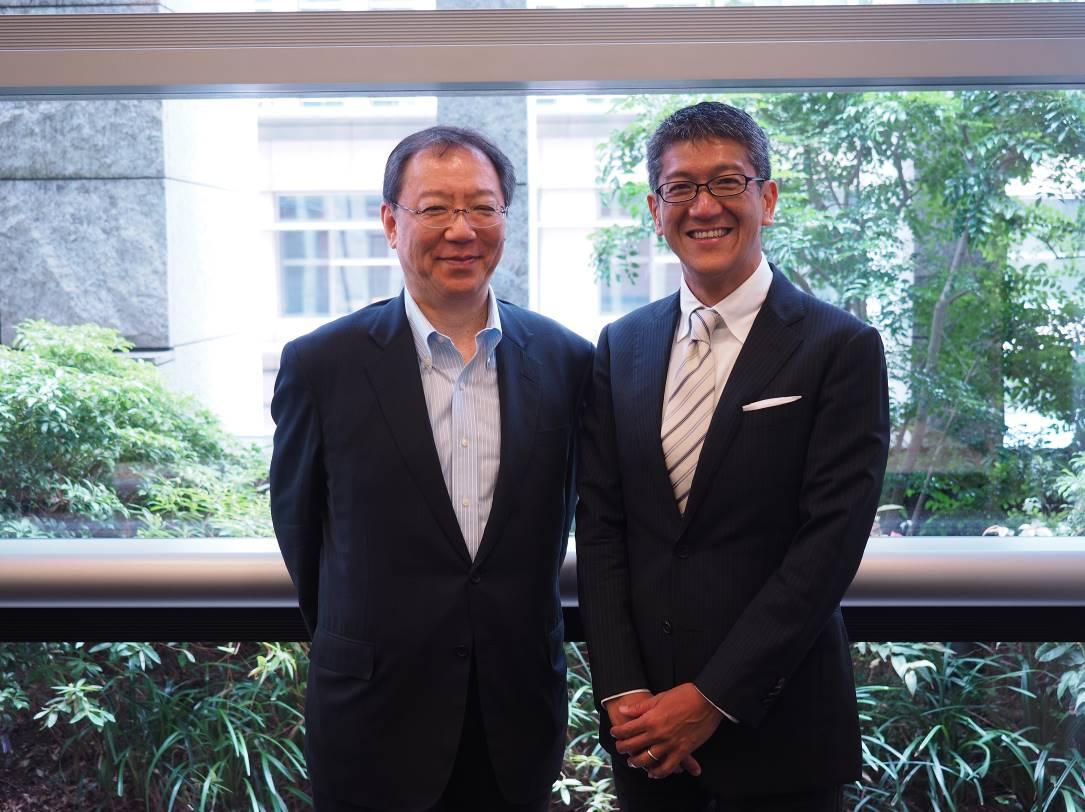
三品和広
神戸大学大学院経営学研究科教授
専攻は経営戦略・経営者論。Ph.D(企業経済学)(ハーバード大学) 1982年一橋大学商学部卒業。84年同大学大学院商学研究科修士課程修了。89年米ハーバード大学文理大学院企業経済学博士課程修了、同大学経営大学院助教授に就任。北陸先端科学技術大学院大学助教授などを経て、2004年から現職。

中神:三品先生は金川さんのことを「明治以来日本に降り立った最高の経営者」だと評していらっしゃいますね。 三品:金川さんや、セブンイレブンの鈴木敏文さんは創業期を経験したのではなく中途入社です。「ワンマン経営」と言われることもありますが、ほとんど資本も持っていません。 一方ダイキン工業の井上礼之さんやセーレンの川田達男さんは新卒入社ですが、同様に優れた経営をしています。 こうしたサラリーマン経営者としていい仕事をした人たちを見ていると共通点があります。それは傍流を経験しているということなんです。 金川さんは商社からメーカーの信越に来ました。でも、せっかくメーカーに来たのに、やりたかったモノ造りをさせてもらえなかった。 当時は本業の塩ビが不振だったので、会社が食いつなぐために一人で海外を飛び回り、製造技術を売り歩いたのです。これは、やらなくて済むならやりたくない、必要悪のような仕事です。一人だけ会社から離れたところで仕事をしていたわけです。 鈴木さんも縁あって出版物の販社から小売業界に来たのに、店の仕事をやらせてもらえませんでした。その代わりに、新店を出すときに地元商店の人をなだめて交渉する仕事をしていました。これもいわば必要悪の仕事です。 二人とも仕事が面白くないので、会社の中に新天地を求めました。金川さんの場合は米国の合弁事業で、鈴木さんは他所から持ちかけられた米国のセブンイレブンという新業態です。そこで自分だけの「箱庭」を造り、会社の中にいながら擬似的に起業するチャンスを得たのです。 だから大企業に一介のサラリーマンとして入社したのに、あたかも創業経営者と同じような経験をしているんです。少なくともその事業については隅から隅まで知っていることが、経営者としての自信になっています。 井上さんは人事部で労組対策をしていましたし、川田さんは幹部候補として入社したのに工場に左遷されました。二人とも会社を中心からではなく、端から見ていたという意味では、金川さんや鈴木さんと同じ経験をしています。 中神:いくつもキーワードが出てきました。新卒も中途も関係ない、傍流に置かれたことで箱庭を造らざるをえなくなった。必要悪のような仕事をしていたので、仕事そのものが辛いし、会社の中で孤独だという意味でも辛い。でもその経験が強い経営者を生み出すことに繋がっている・・・ 三品:ここで凄いのは、セブンでも信越でも当時の主力事業は今やお荷物になっていることです。そして傍流で造った箱庭が大きくなり、会社の事業ポートフォリオが刷新されています。これこそが大企業の健全な延命策です。ポイントは一番有望なエースを、主力事業ではなく傍流に置くことです。 日本企業では優秀な人を採用すると目の届く所で育てようとしますが、本当に優秀な人は他人に育てて欲しくなんかない。勝手に育ちます。だから遠くに追いやり、「15年後元気ならまた会おう」というくらいで良いのです。 中神:それは面白い話ですが、逆に、金川さんも鈴木さんも元々エースではないから傍流に置かれていただけとは考えられませんか? 三品:そうです。彼らのような経営者が育ったのは、偶然のいたずらです。けれども偶然に任せて経営するのではあまりに頼りない。そこで私はそのパターンに学び、意図的に、組織的に経営者を育てる方法があると思っています。それがエースこそ傍流に置くということです。 中神:投資家には、企業には自分が強い領域だけに特化して欲しいという思いがあります。こうしたピュアプレイを求める姿勢と、傍流や箱庭の事業を持つことには相克が生まれませんか? 三品:私はいくつかの会社の社外取締役も務めているので、投資家の立場も痛いほど分かります。でも投資家は売ることができる職業です。極端な話、主力事業で儲かれば次に行けばいい。 一方で企業の中で研究やものづくりを極めている人は、そう簡単には動けません。だから経営者はいつか朽ちゆく主力事業にだけ取り組むのではなく、ネクストステージを創ることを考えなくてはならないのだと思います。
中神:先生の経営者論で面白かったことの一つは、世の中、経営者にあれこれ求めすぎなんだというコメントです。経営者に必要なのは「正しい事業観」、この一点である。それさえ押さえていればいいのに人心掌握とか、人格者であれとか求めすぎていると。 三品:事業観とは、「事業の見方」です。いくら人格者で写真写りがいい経営者でも、事業の見方を誤り事業立地の選択や転換ができなければ、会社は行き詰まります。反対に、優れた経営者は同じ事業でも、他の経営者が見ているのとは全く違う部分を見ています。 例えばゲーム業界でも、カプコンの辻本憲三さんは違いました。他の経営者がいかに面白いゲームを作るか、最先端の技術を盛り込むかを考えているのに、辻本さんだけが在庫管理を考えました。ゲーム会社なのに、ひたすら在庫の数字を見ているわけです。それは、当時のゲームは今のようなダウンロード型ではなくカートリッジの販売なので、ヒットしなければ在庫の山を抱えてしまうから。在庫管理を安易に従業員に委ねると、大量発注で安くしようと在庫の山を築きかねません。 中神:この事業はこれが肝なんだという、独自の感覚を持っていたわけですね。それは他の経営者には見えないものが見えるということでしょうか。 三品:経営者は概して成功物語しか語りませんが、本当は多くの経営者が沢山の失敗をしています。典型的なのはユニクロの柳井正さんでしょう。「一勝九敗」と言っていますが、ユニクロがブレイクするまでは20年近く鳴かず飛ばずでした。でも失敗を重ねるうちに、「あれをやっても上手くいかない」という蓄積ができる。そこから、「簡単には騙されないぞ」という事業の見方ができてくる。だから辛酸を嘗めることは事業観を養う上で大切なのです。 中神:私たちは仕事柄、常にいろいろな会社の成り立ちを見ていますが、事業が物凄く強い会社には、どこかの時代で突出した経営者がいます。その人がここぞ、という点を見極め、同業者の顎が外れるほどのリスクやコストをかけて投資している事例が多いのです。 例えば丸一鋼管という会社。昔は「鉄は国家なり」で、供給側が圧倒的に優位な業界でした。でも丸一鋼管では創業者の妻の吉村タキノさんという人が当時の売上高の何倍という乾坤一擲の工場投資を行い、以後全国で個別受注・即納という顧客第一の体制を整えていったのです。同業者からは「丸一はすぐつぶれるよ」と言われたほどの大投資だったようです。 またトラスコ中山という会社も面白いです。世間一般では「在庫は悪」と言われるのに、中山哲也社長は問屋の機能は在庫にこそある、「在庫は磁石」だと捉え、大型の在庫投資や物流設備への投資を行っています。結果問屋機能が強化されて、自然と顧客が引き寄せられる。成熟した工具卸業界で、しかも最後発企業なのに、シェアをどんどん取って高い成長を続けています。 三品:日本には本当はそういう経営をやる余地がいくらでもあります。 中神:それなのに多くの会社が投資といったら特段の事業観なく、単純に規模を狙っている印象…。規模とは、単に起こった変化の結果に過ぎないと思うのですが、いかがですか? 三品:その通りです。規模の経済は単純で分かりやすいので、日本では過信され過ぎていますね。 「トヨタは大きいじゃないか」と言う人がいますが、トヨタはGMやフォードに比べて胡麻粒みたいな大きさから、今日ほど大きくなったのです。規模の経済を武器にして差を詰めたのではなく、競争力の源泉は別にある。強いから規模が大きくなっただけなのに、多くの人がこの因果関係を理解していません。 中神:でもそういった因果関係を探るには、膨大な調査と地道な分析が必要になりますね。私たちが先生の研究のファンである理由は、他の研究を圧倒するデータとファクトに基づいた帰納的なものだからです。迫力が全然違う。 三品:今書いている『経営戦略の実践』というシリーズは、利益率編、成長率編、占有率編の三部作です。2015年に上梓した利益率編では成功事例を151、失敗事例を101挙げています。今年入稿予定の占有率編は、21世紀の最初の10数年間で占有率が逆転した事例を集中的に取り上げました。成長率編は過去50年の推移を見ているので一番インパクトがあると思いますが、データが膨大なのでまだまだ時間がかかりそうです…(苦笑) でも経営学を語るためには、自分が気に入ったケースの一つや二つでは無理なはず。大学の教授はフルタイムで研究するのが仕事なのだから、みんなそれぐらいやれよと思うんですけどね。 中神:まさに、経営学研究における先生の「事業観」ですね(笑)
中神:ここからは企業と投資家の関係も含めて伺います。先生は、日本企業の戦略不全の核心は、所有と経営の分離に答えを見つけられていないことだとおっしゃっていますね。一方米国はこの半世紀、所有と経営がせめぎ合い、必死に答えを探してきたと。日本において私たち投資家は、この課題にどう取り組むべきなのでしょうか。 三品:所有と経営の分離とは、これまで会社を隅から隅まで知っていた第一人者ではない人が、会社の所有者になるということです。 米国には戦前、ロックフェラーやカーネギーなど偉大な事業家が現れましたが、やがて世代が変わると経営からはパっと手を引き、あとは財団を設立して資本家・所有者として残りました。 それもそのはず。成功したロックフェラー家やカーネギー家で育った子供達はレベルの高い教育を受けて、いい暮らしをしています。そうすると必然的に芸術に興味を持ちます。食うに困らなければ、芸術ほど楽しいことはありません。そういう人が身を粉にして経営するはずがないので、自ら退いてしまうのは正しいことなんです。 日本企業の問題の一つは、会社の事業に興味を失った子や孫に、いつまでも経営をやらせていること。これは本人にとっても、社員にとっても不幸なことです。それよりも会社の中には自社の製品やサービスが三度の飯よりも好きな人がいるのだから、そういう人にやってもらった方がいい。 中神:まずは所有と経営の分離を徹底せよということですね。でもその結果、分離が進んだ会社では株式が分散してしまい、責任あるオーナーシップを発揮する株主がいない中で経営者が生まれてくることになります。 三品:そういう状態は容易に放漫経営を招きます。会社のお金で毎週ゴルフをしたり、どこの会社もやっているからと銀座で食べて飲んで経費を使ったり。ここで私が問題にしたいのは金額の大小ではありません。仮にも経営者の立場にある人が、そんなしょうもないことに時間や体力を浪費していてよいのか、ということなんです。 日本の経営者が本当の意味で経営に使っている時間は、実は凄く少ない。要は「経営もどき」をしているに過ぎない。投資家はそれを厳しく見ていなくてはいけません。 よく考えてみてください。そもそもなぜ経営者が必要なのか―。 経営の一番の要諦は何を社員に任せ、何を任せてはいけないかを峻別することです。例えばモノを造ること。これは客の目があるし、工場には工員の目もある。何よりもメーカーの人はそれがやりたくてたまらないのだから、経営者はすべて部下に任せて一切口を挟まなくていいのです。 でも価格決定は危ない。値段を下げれば客は喜んでくれるし、場合によっては接待をしてもらえる。だから価格決定を社員や営業に任せている会社は、絶対に低収益になります。同様に在庫や経費も危ない。 これはサラリーマンの性質上、仕方がないのです。人間は弱いので、見られているときは頑張るが、見られていないと手を抜いてしまう。人間の宿命です。 社員は最後は自分で責任を取るわけではないので、どうしても甘くなります。そういう部分は、構造的に社員に任せてはいけません。 中神:株主から経営を信託される経営者が、更に何を社員に任せ、何を任せてはいけないかも考えるということですね。しかも仕事の特性や、人間観を併せ持って考えなくてはならない。この峻別を徹底できている経営とはどのようなものなのでしょうか。 三品:例えば日本電産の永守さんが赤字の会社を買ってすぐに黒字転換できるのは、自分で経理台帳をすべて見るからです。会社が大きくなるほど、絶えず見ていないといけない数字が膨大に生まれるのです。鈴木さんや金川さんの場合は前日の営業日報です。 経営者は誰よりも早く世の中の変化に気付かなくてはならない。でも大事な変化は、日々、定点で同じ数字を追いかけていないと見えてきません。 中神:つまり、経営者にもルーチンが存在するということですか。経営者の仕事というものはルーチンからは最も遠く、個別に発生する事象に次々と判断を下していくものにも思われますが。 三品:そこを勘違いしているのは、ヘボな経営者です。今夜は誰と会食だっけ、明日のゴルフは誰と行くんだっけと考えていては、世の中の変化には気が付きません。 ゴルフ場でよその社長に話を聞いて何が分かるでしょうか?果たしてその人が信頼に足る人かなんて分かるでしょうか?本当に人の本質が垣間見えるのは、逆境のときだけです。ゴルフ場の付き合いなんかでは、人の本質は見えません。
中神:厳しい言葉です。最後に、いつも自分にも他人にも厳しい三品先生が、経営者と投資家に問う覚悟を聞かせていただけますか。 三品:世の中で多くの人員を動かすことや大きなお金を動かすことは、一つの特権なのです。その特権を行使する人は、アカウンタブルでなくてはならない。では何のアカウンタビリティが問われるのかと言えば、「本気度」です。 経営でも投資でも、最後に物を言うのは四六時中本気でやるかどうかです。たいていの人は誰かの目がなければ緩んでしまう。でもそんな人に、大事なお金や経営を任せられるでしょうか。何かを委ねられた人は、寝ても覚めてもそのことを考えていないなら、その本気度は嘘です。 日本社会の後進性は、経営者や投資家の本気度がトランスペアレントではないことです。それは政治家も同じ。私たちは社会の重要な地位に就く人の本気度を測定し、開示する仕組みを考えなくてはなりません。 中神:本気度とはいい言葉ですね。投資先企業を見渡すと、友達は少なくて、引きこもってひたすら数字や業務プロセスを睨んでいる経営者がいる会社は本当に強いというのが実感です。私たちはどうすれば本気の人間を創ってゆけるのでしょうか。 三品:本気でやるなら、友達は奥さんだけで十分でしょう(笑)。 私は、世の中には二種類の人間がいると考えています。それは「エンジンを積んだ人」と、「タイヤがついただけの人」。自ら考え自ら進んでいく人と、ただ惰性で進んでいくだけの人です。その違いは、エンジンを積むような原点があったか、そういう厳しい生き方をしてきたかどうかです。 誰かの指示を受け続けていては、人間本気にはなりません。全権委任を受けた人、その結果次第で自分の人生がこんなにも変わるんだということを知った人だけが本気になるのです。 だからトップにできるのは、まず自分が本気でやることです。トップが日の高いうちからゴルフバッグを担いでいれば、それを見た社員も「まあこんなものか」と思います。でもトップが遮二無二やっていれば、弱い人間も少しずつ感化されるものです。 大学教授も同じだと思います。教授になってしまえば息をして瞬きをしていれば、お金はもらえます。それなのに毎日毎日朝早く起きて、誰も興味を持たない資料をひっくり返しているのは、「自分はこれを知りたい」、「これをやらなくてはならない」という強い動機があるからなんです。 中神:私も小さな会社を経営する立場なので、今日の三品先生の言葉は本当に深く胸に刺さりました。トップこそルーチンを持ち、本気でやらなくてはならない。身の引き締まるお話をいただき、ありがとうございました。 2017年7月 日本橋にて ※本誌に掲載されている企業についての言及は、当社の過去の投資実績、現在の投資方針を示唆するものではございません。
編集後記
私たちみさき投資は三品先生の大ファンです。講演があると聞けば必ず申し込んで最前列に陣取りますし、新著が出れば700頁に及ぶ大作でも読み込んで、投資に活かすことはできないか喧々諤々議論をしています。今回のニューズレターも今年の春に人事に関する三品先生の講演を聴き感銘を受け、ぜひもっと熱く経営者論を語っていただきたいとお願いし実現した企画です。 いったい先生のどこにそれほど惹かれてしまうのか…。お話を聞いていて、それは紛れもなく先生の「本気度」にあると思いました。膨大なデータの中から企業経営の真理を見出しそれを世に問うということ。その「マンデート」を全うされようとする姿に、心を揺り動かされるのだと思います。 「大事なことは、血筋でも資本でもない。」これは株主も同じです。単に創業家だから、持分が多いから、と会社の行く末に影響を与えようとしては、一番大切な「良い経営」を見失いかねません。 本気で価値を高めようとしている経営者に、本気で働きかけること。 それが私たちみさき投資の「マンデート」です。 残念ながら運用業界ではこのマンデートという言葉の意味を深く考えず頻繁に使っています。例えば「マンデートを狙う」や「マンデートを取る」。果たしてそのときどれほど使命感を持って本気で取り組んでいるのか…。国民財産の増大という、この仕事の本分を決して忘れてはならないと感じます。 もう一つ、心に残ったのは「自分で一からやることが創業経営者を創る」ということです。みさきはこの10月で会社設立4年・運用開始3年を迎えました。私自身もみさきに参加して3年半が経過します。まだファンドの影も形もなかったときに参加できたことが、設立を応援してくれた全ての人に恩返ししたいという私個人の気持ちに繋がっています。 今年は会社として初めての学生インターンを実施することもできました。協力してくれた若手メンバーとは一から一緒にプログラムを作ることができました。今後会社の規模が大きくなっても、新たな試みを大切にする会社でありたいと思いますし、そうすることでみさきの中から創業経営者を生み続けたいとも思います。 同時にこの言葉からは、流通市場で株式を取得した「中途採用の株主」であっても、会社と一緒に働き一から価値を創ってゆくことで、創業経営者と同じ思いを共有できるはずだという勇気をいただきました。いつか三品先生に「株主と一緒に働くことが経営者を育てる」と言って貰えるように、本気でエンゲージメント活動に取り組んでゆきたいと思います。
リサーチ・オフィサー 槙野 尚