『経営は十年にして成らず』。 今回の対談を終えて真っ先に私の頭に浮かんだのは、神戸大学大学院・三品和広教授の著書名でした… 今回はJT代表取締役副社長・新貝康司さんとの対談です。 JTはもとはと言えば、”専売公社”という国内たばこ事業だけの官僚的体質の企業体だったはず。その会社が今や「日本きってのグローバルM&A巧者」として認められている… 対談前の私の興味は、JTという個別企業のM&A成功ノウハウではなく、JTはなぜそのように洗練された経営をする企業体に変貌できたのか、という点にありました。 対談が進むにつれ明らかになってきたことは、驚くべき経営判断の歴史。 例えば稼ぎ頭のブランドを自ら切って捨てるという決断や、将来生じるリストラを見越した先回りの人事制度改革、そして業績が最高の時こそ希望退職募集や工場閉鎖に踏み切るという大胆な決定等が潜んでいたのです。 世の中に「長期的経営」を標榜する会社は数多くあります。 実際、日本企業の多くが長期的な繁栄を願って日々経営されていることと思います。 しかしJTのように10年先の将来を突き詰めて分析し、やるべきことを順々に、しかもやらねばならないときには必ずできるよう、用意周到に首尾一貫して経営されてきた会社は珍しいのではないでしょうか。 少し前から私は「みさきの公理®」なる考え方を提唱しています。 「企業価値の持続的向上のためには『m』の洗練が大事。『m』はべき乗で企業価値に効いてくる」という考え方なのですが、今回の対談で「mの洗練には順番がある、手順がある」という新たな仮説が生まれてきました。 10年先を見た新貝さんの「着眼大局、着手小局」ぶりをお楽しみいただければ幸いです。
みさき投資株式会社
代表取締役社長
中神康議
中神:新貝さんが2015年に出版された『JTのM&A』は1万部近いヒット作となりました。最近では、「日本でM&Aの上手い会社は?」と尋ねれば、必ず「JT」という答えが返ってくるようになりました。 しかし本日お伺いしたいことはM&Aの成功ノウハウではなく、JTという企業体がここに至るまでの経緯です。専売公社という、意地悪く言えば「大企業の極み」であったJTが、どのようにして日本を代表する「グローバルM&Aの巧者」になったのか?その変容のプロセスに興味があるのです。 新貝:JTの変容は85年の民営化なくして語れません。当時3公社のうち最も強く民営化を希望していたのはJTでした。先輩たちは「グローバル競争下、生き残るためには国際化するしかない。たばこという商品にはそれができる。そのためには民営化が必須。」と熱く語っていました。 民営化当時のJTは「心の豊かさを創造するマーケティングカンパニーになる」という標語を掲げていたのですが、そうなるためにもまずは民営化後の経営基盤の安定が第一ということで、国内たばこ市場の長期予測を行いました。すると人口動態から見て、90年代後半には国内市場そのものが縮小すると分かり愕然としたのです。 このことが国際化志向を一気に高めましたが、当時既にたばこの販売促進や広告宣伝の規制は世界的に強化されつつありました。ゼロからブランドを立ち上げたのでは間に合わないと判断し、小さくてもバリューチェーン全体を買うM&Aを行うことにしました。それがまず92年のマンチェスタータバコの買収となり、そこで研鑽を積んだ人財が99年のRJRI買収で活躍することになったのです。 中神:しかし、ご著書の中ではマンチェスタータバコは「町工場に毛が生えたような会社」と表現されていますよね(笑)。そんな小さなM&A経験だけで、RJRIという大企業の買収・経営ができるようになったのでしょうか?どうやって海外人財を育てられたのでしょうか? 新貝:海外人財といっても民営化前のJTにはせいぜい留学経験のある人くらいしかいませんでした。それでもなんとかしようともがく中で行き着いたのが、「人財貧者の戦略」としてガバナンスを上手く活用することなんです。 RJRIの親会社であるRJRナビスコは当時、投資ファンドKKRによるLBOで借金漬けの状態にありました。ですから子会社から確実に資金を吸い上げることが必須で、そのための強力な権限を持っていました。我々はこのガバナンス構造を活かして、資金の「吸収」ではなく、ブランドや設備への「投資」というアジェンダを入れることでRJRIの持続的な成長に向けて舵を切ったのです。 新貝:一方で痛感したのはJT本社自身のコーポレート・ファンクションが「役所のまま」であったことです。相前後しますが私は89年から96年までの7年間、米国で医薬品の事業開発、特にバイオや製薬のスタートアップ企業とのクロスボーダー提携業務に携わりました。このとき、様々な未知の課題解決、例えば無形資産のバリュエーションといったことが必要になりました。ところが、当時、本社の経理部は前例がないからとか、規程にないなどと言って考えてくれなかったのです。当時のコーポレート機能は、「できない理由」を発明する天才ぶりを発揮していたと言えるでしょう。 これは大きな問題だと思った私は、米国から帰任してからコーポレート各部の管理職に「あなたの部のミッションは何か?顧客は誰か?」と問うて回りました。とりわけエージェントの役割を果たしていた各部は混乱していました。広報はメディアが顧客だと言うし、総務は国会議員だと言うし、経営トップが顧客だと言う部もありました。顧客とステークホルダーをまるっきり混同していたんですね。その中で唯一、当時労働部にいた現社長の小泉だけが「顧客は事業である」と正しい回答をしたのです。 私は小泉を経営企画部の同僚に迎え、官僚化しているコーポレート・ファンクションを変えようと共に手を尽くしました。海外に出るにはどうしてもM&Aが必要ですが、M&Aを行うにはコーポレート・ファンクションがしっかりしていなくては…。手を尽くしてはみたものの、残念ながら改革の手触り感は得られないままでした。 そんな中、98年の鳥居薬品の買収をリードしたのですが、人事部は「知らない人が一気に1,000人も増えてしまった。どうすれば良いのか。」と困って私のところに相談に来ました。このとき私は、M&Aを行うことで「今のままの仕事をしていたら対応できないだろう。」と変革を迫る方が手っ取り早いと気が付いたのです。
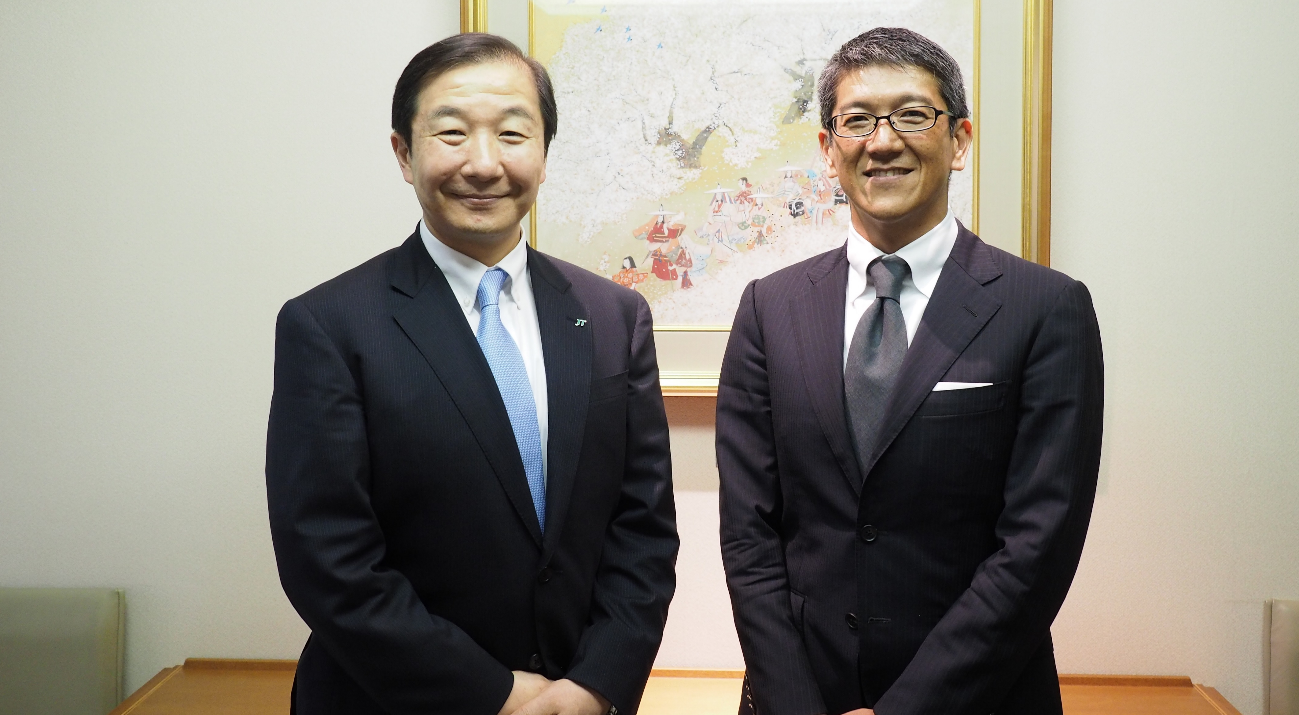
新貝康司
JT代表取締役副社長
中神:なるほど、M&Aをトリガーとして経営改革を始動させたということですね。 新貝:RJRI買収を現地で指揮したのは前社長の木村ですが、日本に残った小泉や私は一緒に、買収を利用して会社を変えてやろうと思っていました。 1999年当時懸案だったのは05年4月に迫った「マールボロ」のライセンス期限です。マールボロはJTの営業利益1,000億円のうち限界利益で400億円ほどを占める大黒柱でした。普通ならライセンスを更新してソフトランディングしようとするでしょう。でもRJRIを買収して世界中で戦っている一方で、国内ではその敵方のブランドに注力しろと言っても士気は上がりません。そこで私たちは98年頃からライセンス更新はやめてしまおうと話していました。 中神:そうだったんですね。私はてっきり、ライセンス期限が来たのでやむを得ずやめたのだと思っていました。能動的にライセンスを切るとは驚くべき決断ですね。 新貝:その後もマールボロは好調で2003年頃には限界利益で500億円ほどにまでなっていました。これは従業員5,000人分の人件費に相当しますし、工場もいくつか閉鎖しなくてはならないレベルです。しかし普通に希望退職を募れば優秀な人から辞めてしまう…。そこでまず、00年に管理職に対して職務給である「ペイ・フォー・ポジション」を導入し、有能な人を抜擢できるような下準備をしました。 ところが02年にいざ合理化計画「PLAN-V」検討プロジェクトを立ち上げようとすると多くの役員から猛烈な反対を受けました。 私も合理化が嬉しいことだとはもちろん思っていません。しかし、どうしてもやらなければならないなら、会社が隆々としていて元気があるときに目一杯の退職パッケージを用意して納得して辞めてもらうことがベストだと思います。だから何としてでも、業績好調な今、やらなくてはという思いがありました。 結局、当時部長だった小泉と私は毎日のように役員を説得して回り、なんとかプロジェクトを立ち上げました。一旦、プロジェクトが立ち上がると当時のトップマネジメントは腹が据わりました。検討して得た成案を、一般社員向けに27回の対話集会を開き4,100人と対話を行いました。このときの教訓はできるだけ多くの人を巻き込み、結論が出るまでやり切るということです。 中神:リストラは切羽詰まってからでは遅く、縮小均衡どころか悪循環に陥ってしまいがちです。かといって、うまく回っているときには中々できないものです。過去最高益が出ているときに合理化計画のPLAN-Vを実施できたのはすごいことだと思います。 新貝:それは90年代後半の金融危機のときに金融機関も事業会社もキャッシュが回らなくなるとあっという間に駄目になるのを見ていたからかもしれません。キャッシュが回らなくなると、まず全従業員に大きな負担をかけます。合理化もままならないような財務状況に追い込まれます。これでは、残った人の士気は上がりません。自分の番はいつかと不安になるだけです。 それよりも利益が伸びているときに感謝の気持ちを込めて退職パッケージを用意し、希望者には徹底的に再就職を支援するべきなのです。船を降りるのも大変ですが、乗り続けて荒波を航海していくのもまた大変なことです。そのどちらを取りますかと問うことは、厳しいですがフェアなことだと思います。こうして会社の体質を作り替えることができました。 もう一つは今後の買収時の借入余力を作ったことです。PLAN-Vでは合理化による一時的なキャッシュ流出を伴いましたが、これで高いキャッシュフロー・利益創出力を有する会社にしていなければ07年のギャラハー買収はできなかったでしょう。
中神:JTは今でこそM&A巧者として様々なメディアで取り上げられ、多くの会社がJTに習えと投資銀行を使わずに自前でM&A部隊を持ったり、Wish Listを用意したりしています。しかし新貝さんの話を聞きながら、そうしたM&Aの技術的なところだけを真似るのではなく、もっと深い経営のレベルから、しかも「順を追って」進化していかなければならないと感じました。 JTといえどもまずは小規模なM&Aで人財を育て、ペイ・フォー・ポジションで優秀な人のコミットメントを確保し、PLAN-Vで十分なキャッシュフローを生める体質に会社を作り替えてきたわけですよね。 新貝:その通りです。もう一つ大切なのは「規範とルールによるガバナンス」を行うことです。M&Aは、会社に異なるバリューチェーンが一気に加わることですから、そもそも社内で規範や価値観を共有できていなければ、特に海外企業の買収などできるはずがありません。 ここでのルールとは、「どこで何が決まるのか」という意思決定の様式のことです。同じ情報を持って意思決定の議論ができるよう、経営情報の見える化を行うこと。また、買収先企業に意思決定権を一定程度委譲するのであれば、代わりにモニタリングのルールを定めておくことが必要です。 中神:新貝さんのお話を伺っていて、これまで私が『みさきの公理®』で並列に扱ってきた経営(management)の「m」のテーマ群にも、実は洗練すべき順番があるのではないかと思えてきました。 海外成長のためにM&Aを軸に据える会社は多いのですが、外国企業の買収などというものは本来、最高レベルの経営スキルのはずです。「m」レベルが低い会社がそのままの姿で成功できるほど世の中は甘くない。 中神:金額も大きくなることが多い。だから業績好調なときにこそ厳しい意思決定を行って、圧倒的な高収益体質に作り替えておかねばならない。そしてその厳しい意思決定のためには情緒的でない判断を下せる人間が要所に配置されていることが必要。だから事前に人事制度や意思決定を属人的なものから公平なルールに依拠したものに変えていく。質の高い意思決定のためには正確な情報が必要ですから、管理会計やITという仕組みの刷新も事前に必要になる。 日本の企業がグローバルで戦い、難易度の高い海外M&Aができるようになるためには、このように順序を踏んでいかなければならないように感じます。 新貝:当にRJRI買収後は管理会計やITの仕組みを強化していくことになりました。買収直後は先行投資がかさむので利益もキャッシュも出ませんが、あるときから急に出始めるのでこれをグループ全体で管理しなくては次の買収に向けられません。ところが新JTI(旧RJRI)の財務スタッフはこのキャッシュを当時は自分たちのものだと考えていましたし、実際JTIのCFOが直接のレポート先でした。これではまずいとJT本体のCFOである私をレポート先に変更しました。これも一種の統合で人財がJTIから流出しないように十分な考慮が必要でした。これにより、JT本体がグループ全体のキャッシュを管理できるようになりました。 ITの活用では電子意思決定システムを作りました。JTIの役員は世界中を飛び回っているので、定例の役員会を開くことは不可能です。そこで電子的に決裁をできる仕組みを整え、今ではJT本体でもこれを採用しています。何時、誰が、どのような意思決定をしているか、見える化を進めると共に、クロスファンクショナルな目の通るシステムになっています。このシステムでは上席者は、部下がどのような意思決定をしたのかを見ることができます。ガバナンス上は「見られている」ということほど効果的なことはなく、そういう感覚を作り出せることにもこの仕組みは意味があると思います。 中神:「m」の順番を意識して海外企業の大型M&Aができる経営力を作っていくとした場合、CFO機能はどのように位置づけられるのでしょうか? 新貝:M&AをやりたいのであればCFOは不可欠です。大規模なM&Aの後には全く異なる文化が会社に加わり、至る所で例外事項やトラブルが起こります。これは企業経営において「有事」と言っていいでしょう。 不祥事や天変地異といった有事にはトップダウンで対処するのに、日本企業のM&Aではトップのコミットメントが見えない事例が散見されます。これはあり得ません。CEOが経営計画のデッサンを描き、CFOが財務的・実務的な裏付けをすることで、初めてM&Aが可能になるのだと思います。
中神:ところで新貝さんはリベラル・アーツをとても大切にしていますね。あるインタビュー記事ではデカルトとAIについて語っていました。経営や経営者にとってなぜリベラル・アーツが重要なのでしょうか? 新貝:それは、それぞれの地域の歴史や文化を理解せずして、世界を相手に事業を展開することはできないからです。 例えばJTは中東で結構なプレゼンスを持っています。これはイランの市場が必ず伸びると考えて先行投資を行っていたためですが、歴史の教科書で主に習う西洋・キリスト教的なモノの見方だけをしていては、経営はうまくいきません。イスラムの世界観から見た歴史も学ぶことで、より良い関係を築き良い経営を行うことができるのです。 哲学、例えばデカルトを考えるということは、これからJTがどのような会社を目指すのかということとも結びつきます。デカルト以前に、今日的な自然科学はありませんでした。彼は要素還元論を発明し、あらゆる事象を要素に細かく分けてそれを解明することで全体を説明できると考えました。その結果発達したのが物理学であり、これを横目で見ていた経済学は「合理的経済人仮説」を置くことで発展しました。私自身は、この経済学のアプローチは誤った考えだと思っています。また、生物学は、もともとは野生の生物体を収集し観察する標本学でしたが、これが分子生物学に発展したのも、「DNAを解明すれば全ての生命現象が説明できる」という一種の錯覚が背景にあります。 ギリシャ哲学では、あらゆるものに意味づけをしようとして今から考えると誤った原理も多く作ってしまいました。一方で、デカルトは身体的な機能に焦点を当て、人間が生来持っている人生の目的、善悪や心は、説明のつかないものとして棚上げしてしまいました。 中世的な世界観の中で抑圧されていた人間の精神性はルネサンス期に花開きました。要素還元論から派生した新自由主義的な経済学により、効率や生産性に支配され、再び心の大切さが置き去りになっているのではないかと思います。 中神:なんだか本日冒頭の「心の豊かさを創造するマーケティングカンパニー」、というJTの標語に戻ってきましたね。 新貝:そうです。先輩がそこまで深く考えて、このスローガンを作ったとまでは思っていません。でも、「たばこ」のような嗜好品には心を穏やかにしたり、落ち込んでいるときに心を元気にする力があります。 これからの時代、AIが人間の職を奪い、人々はますます不安に駆られることでしょう。だからこそ30年後を見据えて、人の心を充足するようなものを社会に提供しつづけていきたいのです。今その先鞭をつけておかなくてはなりません。だから長期を見据えながらも、それを言い訳にすることなく短期的な利益をしっかりと上げることで、長期的な仕事をやらせてもらえる信頼関係を作らなくてはならないと思っています。 中神:短期の業績を上げるために事業や戦略を考えるだけではなく、リベラル・アーツに知見を持ち、長期的な社会のあり方も考察していく。経営は知的体力を総動員する「総合格闘技」だなという感じがしてきますね。 新貝:会社で働くのであれば新入社員から始まり、職位が上がるにつれて社会への責任が段々と重くなります。「私」の部分をゼロにはできませんが、社会のあり方を考え徐々に「公」に置き換えていかなくては、良い経営者になれないのかなと、この10年で思うようになりました。
中神:最後に新貝さんから見て、「投資家はどうあるべきか」ということを聞かせていただけますでしょうか。 新貝:私は10数年前にはCFOとしてよく海外投資家を訪問しました。例えばボストンの長期投資家のところに行けば長期的な戦略を議論でき、それがJTのエクイティ・ストーリーをより強くしてくれました。 しかし最近は長期と言われる投資家に会っても商品の値上げや株主還元のタイミングなど、聞かれることがヘッジファンドと変わらなくなってしまったように思います。特に残念だったのは、投資家が社内アナリストのレポートは読んでいるのにJTの資料は見ておらず、私たちの生の声がフィルタリングされた形でしか伝わっていなかったことです。経営者も同じですが、できるだけ現場を見ること、一次情報に当たることが大切だと思います。 中神:どんな仕事も現場現物主義が大事ということですね。 新貝:そうです。しかし巨大化したファンドはあまりにも巨額の資金を背負わされ、たくさんの投資先を持つことになる…。きめ細かい対応はできないのかもしれません。 その意味では、みさき投資さんのように本当に厳選した企業だけに投資し、常に対話を重ねながら経営知識をアップデートしていかれるのは素晴らしいと思います。 中神:私は上場株式投資という事業は、投資先企業の「経営」に依存するしかない、付加価値の薄い事業だと考えています。こうやって経営者の考えを深くお聞きすることこそが、我々が依存している「経営」というものを学ぶことであって、「投資事業における現場」そのものなのです。 本日はM&Aを切り口にしながらも、経営を洗練していくプロセスについて、示唆に富むお話をありがとうございました。
編集後記
今回、対談の機会を頂きましたJTとは今から2年ほど前、私たちの投資先企業で大型海外M&Aを考えている会社へのヒントをいただいたことがきっかけで、しばしば経営についての意見交換をさせていただくようになりました。 新貝さんはM&Aについてはご著書で余すことなく語っていらっしゃいますが、今回はM&Aを可能にした経営の基盤づくりについても伺うことで、JTの深層にある競争力も見えてきた気がします。また、専売公社という官僚組織を「脱官僚化」してきた経緯は、前回の第6号でディスコの関家社長に伺った「組織を官僚化させないための統治の工夫」にもつながるものがあり、経営におけるシンプルな原則というものが存在していることを感じさせます。 対談の中で登場したデカルトといえば、「我思う、ゆえに我あり」という言葉が有名です。これは「絶対確実なものを見つけるために、世の中全てを疑ったとしても、その疑っている自分自身の存在は疑いようがない」というものでした。しかし経営にも、株式市場にも、絶対確実なものは存在しません。だからこそ多くの投資家はPERやPBRといった相対的な物差しを重宝するのでしょう。 みさき投資では長期投資家として企業の「絶対価値」を見極めたいと考えています。でもそれは他の全てを疑う唯我独尊の営みではありません。むしろ、神のみぞ知る「絶対価値」に少しでも近づくために、経営者とも従業員とも、取引先とも、時には競合企業とも、信頼関係を築き対話してゆくことの積み重ねです。 そうやって(当たらずとも遠からずの)絶対価値という拠りどころを持てた際には、市場の陶酔には冷静に、悲観には果敢に向き合うことができるはずです。嗜好品としてのたばこが人の心を穏やかにするように、みさき投資も市場の荒波の先を照らし穏やかで安定した長期経営を支える岬でありたいと思います。
リサーチ・オフィサー 槙野 尚