「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とはドイツの鉄血宰相と呼ばれたビスマルクの言だそうです。 彼が実際にその言葉を発したかどうかは判然としませんが、人間は一般に、自分自身や身近な人々の実体験に過度に影響され、長い時間軸や洋の東西を見渡した思考が不得意だという指摘は正しいと思います。 日本のコーポレートガバナンス改革は、2014年に発表された「伊藤レポート」から数えても8年目を迎えます。「歴史」を重ねたとも言えそうですが、やはりホンの短期間の、しかも日本という狭い国の「経験」という方が正確だと思います。 今回のみさきニューズレターは、斉藤惇さんをお迎えしました。斉藤さんはいまを遡ること約半世紀前に米国で始まった世界的ガバナンス改革の「源流」に触れ、商事法務等で早くから先進的な論考を発表。その後も産業再生機構社長や東京証券取引所社長を歴任しつつ、わが国のガバナンス改革のうねりを形作ってきた方です。 (それがガバナンス改革であろうがなかろうが)世界という広い舞台で長く続いている潮流には、必ずシリアスな「源流」があり、その後も差し迫ったリアリズムの連続があるはずです。 では、かの国がガバナンス改革に乗り出さざるを得なかった必然とは何だったのか、その後も続いた抜き差しならない状況とは何だったのか…。 丹念に源流を振り返りながら、斉藤さんの温かくも厳しい眼差しは、いまの日本に向けられていきます。そこにはガバナンス改革というテーマすら手段と捉えなおし、「社会の変革」こそを目的と置きなおす大きな視座がありました。 そしてその大目的のためには、人間が持つ美しい心だけでなく、ともすると忌み嫌われがちな「グリード」すら使い倒すべき、という圧倒的な現実主義が…。 今回も、みなさまの長期・多面・本質的思考を十二分に刺激するニューズレターになっているとすれば幸いです。
みさき投資株式会社
代表取締役社長
中神 康議
中神:今日はコーポレート・ガバナンスをドライバーにした社会変革、という大きいお話を伺いたいと思います。幸運なことに、私は斉藤さんの謦咳に触れる機会はこれまで何度もあったんですけれども、2021年のコーポレート・ガバナンス大賞フォーラムのときの、斉藤さんの強烈なメッセージ、歴史観に根差した「上場企業の取締役というのは、ある意味、公職なんだ。そのくらいの責任感と気概でやってもらわないと困る」というお話を伺って、一度、ガバナンスの源流のところからお話をお伺いしてみたいと思って、お時間を頂いた次第です。 斉藤さんはなぜコーポレート・ガバナンスに関心を持たれたのでしょうか?アメリカで長くお仕事をされてきましたが、あの国はそもそもなぜコーポレート・ガバナンスの世界に入っていかざるを得なかったのか、この辺りの歴史からお伺いできますでしょうか。 斉藤:もちろん私が全ての背景を知っているわけじゃないですけれども、ウォール・ストリートで見聞きしたことをベースにお話していきましょう。コーポレート・ガバナンス、つまり企業は誰のものかという議論は、1930年代にはすでにアメリカではかなり論争があったんです。ただアメリカに駐在した1970年代当時、私自身はよく分かってなかった。 アメリカで自分が現実の事象として見たのは、幾つかの年金改革でした。1974年頃、ベトナム戦争が終わるか終わらないかというときのアメリカは、ものすごくすさんでいました。そんなときに、こともあろうにニューヨーク市の財政が破綻して、ビッグマックと呼ばれる市債が償還されないという事件があったんですね。みんなが頼りにしていた公共債が償還されないというので、バンカース・トラスト銀行の周りには、ガーッと人の列ができて。 中神:ニューヨーク市の市債がデフォルト(債務不履行)を起こすという、いまでは考えられないようなことが起きてしまったわけですね。 斉藤:当時、ベトナム戦争の影響で経済は急速に減速し、もうアメリカは駄目になるというムードだったんですが、その状況下で、市債がデフォルトしてしまった。そうすると、フィフス・アベニュー(ニューヨーク五番街)でさえも修理できず、穴ボコだらけになったんです。ウェストサイド・ハイウェイ(ハドソン川沿いにマンハッタン南部を走る高速道路)という道が今もありますが、この道路が朝、通勤中にウォール・ストリートのちょっと手前でドーンと落ちた。この道路は1929年から1951年の間に建設されたものですが、メンテナンスが悪いものですから落ちちゃって、落ちたまま何年も置いてあって…。 中神:市の財政が破綻しているので、資金がなくて道路を直せないわけですね。 斉藤:治安も悪く、イタリアマフィアがレストランで本当に機関銃を撃ったりしていました。映画そのまま、あの通りなんです。女性が朝の通勤列車の中でレイプされるとか、コロンビア大学の先生が地下鉄から大学駅に上がった途端に強盗に遭って、お金を渡したけれど財布に少し残していたので撃たれて死んだとか、そういうすさまじい状況です。 中神:今では想像もできませんね。市の財政が破綻してインフラはボロボロで、治安も悪いという社会環境ですから、人々は現在の生活にも将来の生活にも不安を抱えながら生活されていたことと思います。 斉藤:そういう社会状況の中で何があったかというと、自分たちは将来本当に年金で食えるのかと、国民がものすごく恐怖感を持って騒ぎだしたんです。当時、アメリカの株式市場は、60年代のニフティ・フィフティという、それ行けどんどん的な上昇相場の後でしたから、年金の運用はもう投機の場でした。ちゃんとした制度で年金の運用が管理されていなかった。 そこでフォード大統領の末期の頃だったと思いますが、年金の運用をしている人間に責任を取らせなければいけないという声が出始めました。そしてプルーデントマン・ルールとかフィデューシャリー・デューティーとか、要するにジェントルマンの善意を持って運用をする。少なくとも誠意を持って運用をしなきゃいけないというルールが施行されました。それに反した場合は懲役何年という刑罰を科する。ここが日本と違うんですが、行政罰ではなくて刑事罰なんです。これにはすさまじい影響力がありました。 中神:刑事罰を受けるというのは、実際に年金担当者が刑務所にいれられてしまうのですか? 斉藤:はい。いい加減な運用をしていた連中を、次から次にSECが訴追して、検事・検察が動いて捕まえて、刑務所にぶち込むわけです。だから不正運用をしていたファンド会社がブラジルへ逃げ出すなんて事件もありました。 中神:それは相当なインパクトがありますね。 斉藤:それでも米国の株式市場が上昇しているうちは良かったのですが、下落に転じると、年金運用パフォーマンス悪化の責任論が起こった。そして年金運用者が「俺たちだけ、こんな厳しい法律の網をかけられていては、かなわない」と言い出した。 それから年金運用担当者は、自分たちの運用資産が大きいために、株を売り買いするとマーケットインパクト(=自分で相場を動かしてしまうこと)が非常に大きくコストがかさむと言っていました。このマーケットインパクトをどうやって軽減するかということから、「売り買いしないで、株を保有したまま会社をよくすればいいのだ」という理論が、カルパースやカレッジ・リタイアメント・ファンドのような年金ファンドから出てきたわけです。 中神:短期的な投資家だと株を売り買いすることでパフォーマンスを向上させようとしますが、年金のように大きな資産を扱う投資家は株を売り買いするとマーケットインパクトが大きい。だから長期投資家として株を保有し続けたまま、会社をよくすることで年金基金のリターンを上げていこうとした訳ですね。 企業に長期で投資し、その事業を良くすることでリターンを得ようとする発想は、みさき投資も同じです。 斉藤:さらに、戦前にあったコーポレート・ガバナンスの議論がこれに加わりました。会社は誰のものなんだというとやっぱり株主なわけですが、株主といっても実際のところは投資信託や年金なので、実は年金こそが企業を所有しているんじゃないかという理論に展開していきました。年金=大衆ですから、「大衆が企業をウォッチする」という、非常に耳障りの良い資本主義が促進されていくわけです。そしてその過程の中で、アメリカ企業の効率が様変わりし始めた。
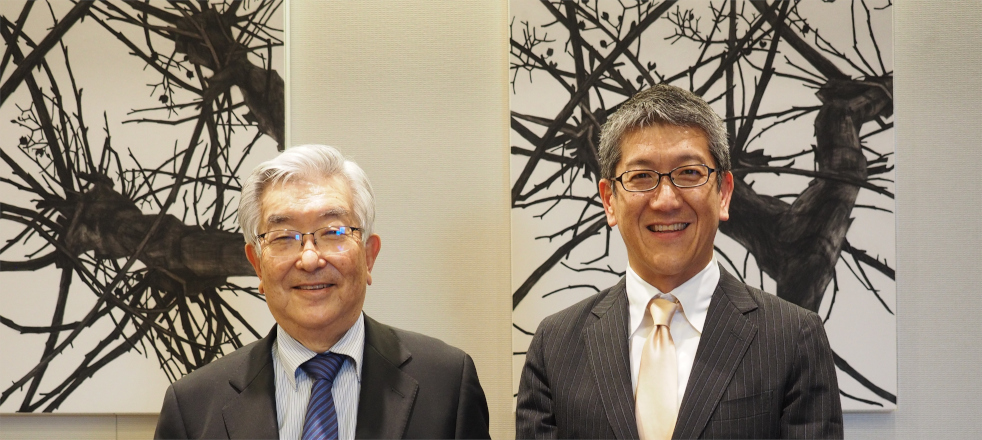
斉藤 惇
KKR Global Institute シニアフェロー日本野球機構会長
野村証券株式会社代表取締役副社長、住友ライフ・インベストメント株式会社の代表取締役社長・会長等を歴任した後、株式会社産業再生機構の代表取締役社長として日本の不良債権問題解決や企業の事業再生に貢献。 <p> その後、株式会社東京証券取引所グループの取締役兼代表執行役社長、株式会社日本取引所グループの取締役兼代表執行役グループCEOなどを歴任</p>
中神:アメリカはベトナム戦争後のどん底から、年金改革によりコーポレート・ガバナンスが促進されたことで、企業の生産性が改善してきたわけですね。一方で、1970年代というと日本は高度経済成長期ですが、アメリカは日本型のコーポ―レート・ガバナンスをどのように見ていたのでしょうか? 斉藤:高度成長期の前をきちんとひも解いてみると、戦前の日本は、実はびっくりするほど徹底的な資本主義の先端をいっていました。まさしく株主資本主義で、三井家や岩崎家は企業から利益をギューッと絞りとる。所有と執行の分離が出来ており、番頭さんというのは執行サイドでした。取締役にも内部昇進者だけではなく、株主の代表もかなり入っていた。さらに役員報酬は利益とリンクしてかなり高額でした。それに対して、まだアメリカは資本主義がヤワだったんです。日本の方がよっぽどきちっと所有と執行の分離ができていた。 中神:米国と比較して、日本の方が所有と執行の分離ができていたというのは、今と全く逆の関係ですね。 斉藤:真逆ですね。ただ、第2次世界大戦に突入する過程で、日本政府はソ連をモデルとした経済計画にならい、経済統制を強めた戦時体制を築くんです。この影響は企業のガバナンスにも及び、高率配当を許可制とし、役員賞与にも制限がかけられ、配当や役員報酬は利益とリンクしなくなってしまった。また従業員の士気と生活水準を高めるため、株主の力は制限され従業員の地位が向上します。従業員から役員に登用される者も増加したんです。金融にも規制がおよび、企業の資金調達を直接金融から間接金融に誘導し、メイン・バンク制を産むきっかけとなりました。 中神:戦時体制によって、最先端だった日本の資本主義・コーポレート・ガバナンスが後退してしまったということですか。これは知りませんでした。 斉藤:面白いのは、戦後、アメリカは、戦時中に作られた制度を完全にはつぶしていないんです。たとえばマッカーサーは終身雇用制度などを認めているので、戦時体制の中で作られた制度が半分くらい残って現在まで続いている訳です。 中神:年功序列と終身雇用は日本型経営のかなめで、日本の伝統・企業風土と多くの人が信じていると思いますが、実はこれは戦時体制下に人工的に作られた制度で、その一部が戦後残り、定着していったものなんですね。 斉藤:そうなんです。一方1970年代、アメリカでは終身雇用制度に代表される日本型経営に関心が高まりました。当時すでに、ハーバード大学のマイケル・ポーターは日本のステークホルダーズ経営に興味があって、アメリカも日本のようにいろいろなステークホルダーズに配慮した経営をやったらいいんじゃないかという議論がありました。というのは、「いったい、なぜ日本は成功しているんだ」というのがテーマだったからです。 中神:アメリカは株主資本主義を進めているが、成功している日本は株主だけでなく従業員・顧客などいろいろなステークホルダーズに配慮した経営をしている。これが日本企業の成功の理由なのではないかと考えたのですね。 斉藤:私も、プリンストン大学とかハーバード大学の法学部の先生に呼ばれて、「日本はどうしてアメリカを打ち負かせるんだ?」とか、「日本の経営の真髄って、いったい何なんだ?」と聞かれました。 アメリカは、日本の終身雇用制度にも、ものすごく関心を持ったんです。「トヨタの従業員は、給料は低いのに、会社に対するロイヤリティーがなぜ高いのか」と聞かれると、「トヨタは、貧しいところの子でも、優秀な子は中学校くらいの時代からトヨタの学校に受け入れて、終身で面倒を見るんですよ。」などと、私も良い格好をしていろいろ言っていました。 中神:いろいろなステークホルダーズに配慮した日本的な経営というのが、当時の米国にとっては興味深かったんでしょうね。 斉藤:終身雇用というのが日本の生産性を相当に高めているというのが、当時のアメリカの結論だった。今と逆さまでしょう。 中神:全く逆さまですね。

斉藤:当時、本屋に行くと、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』とか、『第二次世界大戦のしっぺ返しが始まった』とか『やり返すジャパニーズ』とか、そういう本がいっぱい出ていました。はっきり言うと、日本人に対する感情は必ずしもよくなかった。我々も、ジャップなどとよく言われました。それは、やっぱりまだ戦争が終わって何十年しかたっていないから、「また、やつらがやって来たぞ」という意識があった。 中神:日本製品が叩かれた時代ですね。 斉藤:それがいつの間にか、アメリカの経済が復活する一方で、日本の経済は競争力を失っていくわけです。残念なことは、ここで日本の分析が足りなかったことです。これが今にも続いているんですが、私はプラザ合意と、1989年の日米構造協議の影響が大きかったと思います。 アメリカは「円がどうも弱い。これで日本はアメリカに侵入してきているんじゃないか」というような、国際競争力の低下に対応して為替レートなどのマクロ経済からのアプローチや、自動車の輸出量等の規制をかけることで、競争力を回復しようとした。 中神:アメリカはそこまでして、何としても企業の国際競争力を回復させたかった。 斉藤:米国の国際競争力の回復の源泉は、必ずしもコーポレート・ガバナンスによる企業の収益性の改善だけではない。 ただはっきりしていることは、政治も日本にやられてたまるかとやるし、企業はちゃんとエフィシェント経営をやれ、国民の年金を守れ、とやる。国を挙げて、米国の競争力を取り戻そうとしたんです。
中神:アメリカでは、国際競争力低下に対応するためにマクロ的アプローチだけではなく、ミクロ的なアプローチ、つまり年金改革を通じてコーポレート・ガバナンスを強化したことで、実際に企業が変わってきた。アメリカはそうした大きな道筋を考えて、大胆に社会を変革してきたという点を非常に興味深く感じます。 一方、日本では株主の力を使って企業を変革していくということについては、依然として大きな抵抗感がある。こうした違いはどこから生まれるのでしょうか? 斉藤:日本とアメリカでベースになるカルチャーが少し違うのは、アメリカの場合はやっぱり勝者・敗者というものを認めるわけです。だから、能力があり努力して株価が上がったら勝者であり、やらなくて株価が上がらなかったら敗者なんです。ものさしがはっきり見えているから、社会全体が勝者に向かって走るわけです。 そして社会制度も勝者を利用しよう、勝者をつかまえた社会というのをつくろうとしますから、社会全体が非常に合理的であり説明性があり効率性があるんです。私が日本にやってほしいのは、そういう社会制度を作ることです。 中神:日本には優勝劣敗をちゃんとつけるとか、それをドライバーにしながら社会の富を生んでいくというロジックがあまりにもなさ過ぎるということでしょうか。 斉藤:コーポレート・ガバナンスは勝者・敗者をしっかり認めた上で、少なくとも「敗者にはなるな」、「勝者になれ」ということでやっていくべきです。そして、そのときの手段の合理性とか倫理性というのを見ていくのが、社外取締役であるべきです。社会と言っても、そうやって動く会社群の塊として社会ができているのですから、まずはミクロの会社がそうやって変わらなければならない。 勝敗の結果としてそこで差が出たものを調整するのは、もう政治の世界。税金とかで調整すればいいのであって、それはまったくの別問題です。 中神:まず民間は、徹底的に勝敗にこだわる。もちろん倫理は大事にしたうえで。そして勝敗や格差を調整するのは政治サイドのテーマ、と切り分けるわけですね。 日本では、小学校の徒競走においても順位をつけない学校があったり、何でも平等でなければならないという思想が強いのでしょうかね。 斉藤:小説なんかを読むと、実は日本には猛烈な優勝劣敗の世界があった。ただ同時に、田舎にお金がなくても優秀な子がいると、素封家がその子供を学校へ行かせてやるといったこともあったわけです。 つまり、豊かになった人はそうでない人を救ってあげるという社会をつくればいいのであって、それをやらないから問題なのです。ビル・ゲイツだって財団をつくってものすごく寄付しているでしょう。ジェフ・ベゾスだって、豊かになった人に増税しろと言ってるじゃないですか。それが倫理というものです。それがモラル。日本はそれをやる前に、「そういうのは厳しいから、みんなで等しく貧乏になろうぜ」と言っている。 私は橋田壽賀子さんが亡くなってしまったことを非常に残念に思います。あの人は、「苦労した者が報われる」ということを是とした人ですよね。そこに日本の戦後の苦労というのが重なって、一つの小説になっているわけです。 中神:「おしん」とか、「渡る世間は鬼ばかり」の世界ですね。僕が子供の時は、その手の風潮が日本中にあったような気がします。 斉藤:効率性のある社会というのは説明性も求められるし、ある意味では非常にフェアなんです。「曲がった効率性」などというのは長持ちしませんから。古いものをいつまでも置いておけばだんだん収益性が悪くなるから、それをディスラプトし、リモデルする必要が出てくる。会社自身でそれをできないなら、PE(プライベート・エクイティ)などにカーブアウトしていいと思うんです。 中神:「社会をよくする原動力は何か」ということを、直視しなきゃいけないということでしょうか。社会をよくする原動力は、間違いなく人間の本性だと思うんですけれども、本性の中にグリードもあれば、慈愛の心みたいなのもある。大成功したら、本当は人間には慈愛の心が自然に生まれるわけですよね。そういうものをちゃんと直視して使っていく。 そのためには、まず優勝劣敗をつけるというロジックがすごく大事で、これは企業の優勝劣敗もつけなきゃいけないし、アセットマネジャーの優勝劣敗もつけなきゃいけないし、アセットオーナーの年金の優勝劣敗もつけなきゃいけない。「優勝劣敗が貫徹されること」が、社会を変える原動力になるということですね。 斉藤:それで世の中が強くなり、GDPも伸びて、株価の上昇で年金も改善し、結果的には皆ベネフィットを受けるわけです。
中神:なるほど、なるほど。日本でも会社を強くするという目的をもってガバナンス改革が進んできたと思うのですが、日本のコーポレート・ガバナンスに足りないものとは何でしょうか? 斉藤:コーポレート・ガバナンス、社外取締役、ROEとか言葉は同じように使っているんですが、日本は「コーポレート・ガバナンスが社会制度になっていない」と思います。ROEという数字だけ形をつくっても、社会が変わらないと意味がないと私は思う。 ほんとうは「日本は、ROEは5%だけれども、こういう制度でやっている。それで社会はうまく回っている」というものがあればいい。以前は、「ROEも低いし配当も低い。持ち合いだけれども終身雇用で生活の不安がない」という国だった。しかし、いま、それが持続できなくなった。次にどういう社会を求めるのか、どうやって社会を強くするのかというロジックをつくらなきゃいけないですよね。 日本は小さい国ですから、合理的で力のある企業が30社から40社、出てくればいい。そうすれば、もう十分、国がピリッとしてくると思う。そういう点で、社外取締役というのはものすごく重要な使命を持っているはずなんです。大いにいろんな人がなってほしい。社外取締役の数を求めたということ自体は否定しませんけれども、ちゃんとミッションをつけてやらないといけないし、社会に対する責任を持たなくてはならない。 中神:社外取締役には単にその会社を変えるというだけでなく、「社会を変えていく」というミッションがあると。 斉藤:その通りです。だから、社外取締役というのは単に「就職」感覚じゃ駄目なんです。就職感覚で社外取締役になる人には、「お願いだから、やめてくれ」と言いたいわけ。「自分は、金は要らないけれども、日本のために、何としてでもこういうことをやらにゃいかん」と思う人にやってもらわないといけない。 中神:古いものを置いておけばだんだん収益性が悪くなるからディスラプトしたり、リモデルする必要が出てくるというお話がありましたが、そういったディスラプションを仕掛けていくというのも、社外取締役の大きな役割なのでしょうか? 斉藤:そうだと思います。ディスラプションというのは、自分でできる経営者ももちろんおられるけれども、なかなか勇気が要ると思うんです。ディスラプションをしなきゃいけない企業というのはかなり問題があるところが多いので、やっぱり正論をもって攻めてくる外部の圧力があればやりやすい。 中神:経営者は、ディスラプションするためには社内を説得しなければならない。その際に社外取締役だけでなく、株主が経営者に寄り添い、経営者の戦略を支持し応援し続けることで改革が進みやすくなるはずです。社外からの力というのは、経営を動かす大きな力になりうると思います。
斉藤:日本は、ちょっと前まではGDPだろうが生産性だろうが、どの数字を取っても少なくとも5位以内に入っていたような国だったわけです。それが、戦争もしていないのに何故今では27位とか30位になってしまったのか、根本的にどこに問題があったのかということを、誰もちゃんと経営面からは分析していない。 私の結論は、結局、誰も「自らを破壊できなかった」ということです。成功体験を守ることだけが経営者の仕事だった。先輩がやったことを崩さない。先輩が失敗しているケースを引き継いだ人は新しいイノベーティブな仕事をしたいのだけれども、いい会社と言われるところであればあるほど壊せない。 しかし、状況は時代とともに変わってきているはずで、今までものすごく稼いだものが稼げないということが、いろいろなところで既に起きているわけです。それを構造的な問題なのかサイクルの問題なのか分析をして、構造的な問題だと思ったら、これはもう壊すしかない。 中神:経営者は、問題を抱える事業が自分を社長に指名してくれた顧問や相談役たちが開始した事業の場合に、事業撤退に遠慮が働くということもありますよね。であるからこそ、しがらみのない外部の人間が、客観的に構造改革を求める意味は大きい。 斉藤:今、コーポレート・ガバナンスは新しい局面に来ています。今の日本の経営構造では、伝統的なものに固執するがゆえに変えられない、あるいは変えないことが良い、という風に思われてしまっている。それではどうやったら「いや、そうじゃない」という新しいチャレンジ、ディスラプションができるかというと、やっぱりある意味の「外からの圧力」が必要。それには株主のグリーディーな力を少し使う。 株主はグリーディーです。それは全く否定しない。株主が神様みたいなことはあり得ない。株主は、やっぱり基本的に株価が上がって、儲かればいいと考えている。問題は株価の上昇は企業価値の上昇を反映したものであらねばならないという事です。そういうグリーディーな力を使って社会をどう変えるかが課題なのです。 「グリーディーなだけの社会」にしてしまっては駄目なんだということ。株主にはこの程度までやらせながら、これ以上はやらせない。しかし、常にカンファタブルな位置付けは与えておくとか。そういう戦略がなければならない。 もう本当に我々が住んでいる社会そのものをこの力で変えないと、日本が世界についていけない社会になってしまう。はっきり言うと日本は、もう、その入り口にいると思うんです。 中神:日本の「社会」を変革していく上で、株主の役割は非常に大きいんだなと、改めて身が引き締まる思いです。みさき投資も企業経営者や従業員の方と共に働き、日本の国際競争力の復活のために邁進したいと思います。今日は、すごく大切なメッセージをたくさん頂きありがとうございました。 2021年4月 丸の内にて ※本誌に掲載されている企業についての言及は、当社の過去の投資実績、現在の投資方針を示唆するものではございません。 PDFはこちら
編集後記
このインタビューが行われた日から、ちょうど1年前の2020年4月、日本政府は新型コロナ感染症対策として、はじめての緊急事態宣言を行いました。対象地域の住民は、生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛が求められ、お店の営業や、個人の自由な行動が制限されました。「個人の利益」と「国家全体の利益」のどちらを優先するべきなのかという問いは、法哲学や国家論の根本問題であり、アリストテレスをはじめ古くから論議されてきたテーマですが、新型コロナは国家の利益のために個人が為すべきことは何かを考える新たなきっかけを与えてくれました。 斉藤さんは、「上場企業の取締役というのは、ある意味、公職なんだ」と述べています。公職とは、国家全体への奉仕者であり、その利益のために働く人です。企業が不採算事業を売却することは、必ずしも関係者全員の利益になる話ではありません。企業経営者にとっても、非常に厳しい決断であるはずです。ただ経営者が過去の成功体験を守り続け、自らを破壊できなければ、会社の生産性のみならず、国家全体の生産性が下がり、日本は世界から取り残される存在になってしまいます。 年金資金を預かっている以上、みさき投資で働くことも公職だと思います。無論、運用するファンドではリターンを追い、我々自身も他のアセットマネジャーと比べられ、優勝劣敗がつく世界に生きています。社会として勝者・敗者を認めることは時として厳しい面もあります。また勝者のみを賛美し、勝者が敗者を思いやることのない社会は、豊かな社会とは言えません。ただ、「社会を変えるドライバーとは豊かさを求める人間の本性である」と斉藤さんは述べています。リターンを求める株主の存在は、企業を変革する力に成り得るはずです。私もみさき投資の一員として、企業経営者や従業員の方と共に働き、日本の国際競争力の復活のために邁進したいと思います。
マネージャー 古川 周平